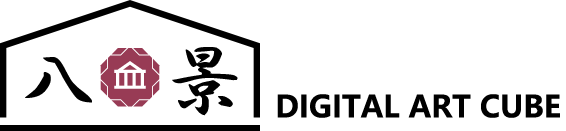日本美術史に於いての"核"と"根幹"展
中古・中世・近世・近代という系譜で日本の書画は発展を遂げて行きますが、そこには時代別に応じた発展と価値観に応じた需要が存在し成り立っていきます。
島国である日本の文化は、大陸文化とは異なり独自の"美意識"や"情緒"と言う内面を表しています。
信仰・文化・需要・反映・と言った成り立ちを日本美術史で最も重要な"核"と"根幹"であるべき書画と言う分野を通して感じて再認識頂ける事を願っています。
島国である日本の文化は、大陸文化とは異なり独自の"美意識"や"情緒"と言う内面を表しています。
信仰・文化・需要・反映・と言った成り立ちを日本美術史で最も重要な"核"と"根幹"であるべき書画と言う分野を通して感じて再認識頂ける事を願っています。
第1期 絵画資料
本展は作品を五つのカテゴリーに分け。ここでは第1期絵画資料として12点の作品を展示しています。絵画・書簡などに於いて、表面的な部分以外を楽しむ事の一つに、資料と言われる分野が存在します。画や書は勿論表面的に眺めて楽しむわけですが、資料と言われる点は、どちらかと言えば、考え情景を思い描きながら楽しむ事が出来る分野です。 表面的に楽しめる事よりさらに深く入り込み悩み、自分なりの見解を紐解いていく事が資料と言われる点の面白さでは無いかと思います。
江之島金龜山三宮細見之圖
作者不詳
江戸中期-後期
紙本着色
個人蔵
68.5 x 103.0 cm
上之宮藏板の『江之島金龜山三宮細見之圖』の原本と思われる作品。 部分的に特に厚塗の岩絵具にて彩色を施し、大まかには薄墨にて輪郭線を描いている。良質な金彩朱彩にて色を刺し、海一面は群青絵具の濃淡で抑揚を表現し、波のラインは薄墨を用い細筆にて丁寧に描かれている。
描かれた時代は箔や原料などから江戸中期〜後期、同時代には極めて近しくも吉田蘭香画『江之島金龜山三宮細見之圖』上之宮藏板とは構図の異なる箇所も多く、更に調べて行く必要がある。
作者不詳
江戸中期-後期
紙本着色
個人蔵
68.5 x 103.0 cm
上之宮藏板の『江之島金龜山三宮細見之圖』の原本と思われる作品。 部分的に特に厚塗の岩絵具にて彩色を施し、大まかには薄墨にて輪郭線を描いている。良質な金彩朱彩にて色を刺し、海一面は群青絵具の濃淡で抑揚を表現し、波のラインは薄墨を用い細筆にて丁寧に描かれている。
描かれた時代は箔や原料などから江戸中期〜後期、同時代には極めて近しくも吉田蘭香画『江之島金龜山三宮細見之圖』上之宮藏板とは構図の異なる箇所も多く、更に調べて行く必要がある。

阿蘭陀猿図
作者不詳
1795年
紙本着色
個人蔵
27.5 x 114.0 cm
寛政七年(1795年)、極めて細密に描かれた阿蘭陀猿図。
猿画の名手としてまず名が上がるのは森狙仙であるが、本作は狙仙の作品に劣らない写実性を備えており、特に毛描きや、猿画で重視される手足の描写からは、画力の高さがうかがわれる。なお、江戸絵画では、日本猿は尾を短く、実物に忠実に描くのが通例であるが、本図は、阿蘭陀から舶来された猿を写生したものと思われ、日本猿に似た姿ながらも尾だけが特徴的に長い。絵師が当時、珍しい舶来の猿の『阿蘭陀』的な部分を、どこに見出していたのかもうかがえる、興味深い作品である。
作者不詳
1795年
紙本着色
個人蔵
27.5 x 114.0 cm
寛政七年(1795年)、極めて細密に描かれた阿蘭陀猿図。
猿画の名手としてまず名が上がるのは森狙仙であるが、本作は狙仙の作品に劣らない写実性を備えており、特に毛描きや、猿画で重視される手足の描写からは、画力の高さがうかがわれる。なお、江戸絵画では、日本猿は尾を短く、実物に忠実に描くのが通例であるが、本図は、阿蘭陀から舶来された猿を写生したものと思われ、日本猿に似た姿ながらも尾だけが特徴的に長い。絵師が当時、珍しい舶来の猿の『阿蘭陀』的な部分を、どこに見出していたのかもうかがえる、興味深い作品である。



狩猟土人三幅
作者不詳
制作年不詳
紙本着色
個人蔵
34.5 x 151.0 cm
本作について、福島宣三(参院議員)に見解を問われた末松謙澄は、『初期油彩画では無いか』との回答を寄せた一方、後藤貞行(彫刻家・洋画家)は蘭画の様式に触れたうえで、『ヨーロッパの油彩では無いのではないか』、『古代の画』といった漠然とした見解を遺している。
来歴や絵筋、画題、上部に描かれた数字やアルファベットの様な物の意味など、詳らかでない部分の多い作品である。数字やアルファベット表記は、阿蘭陀由来の絵画にもしばしば存在するが、満洲系の文字に酷似する箇所もあり、こちらも詳細は不明である。
三幅にはそれぞれ、中央に背を向けた人物、向かって右には弓を持ち衣を纏った人物、左には素足のまま袋のような物を提げる人物が描かれている。
右と中央の2名には服飾が描かれているのに対し、左の1名だけは羽織のみを纏った使用人のような出立で、他の2名とは明らかに異なる表現されている。様々資料をあたったが、浅学のため、このような浅黒い肌の描写に類例を見いだせないので、詳しい方よりご教授いただきたい。
作者不詳
制作年不詳
紙本着色
個人蔵
34.5 x 151.0 cm
本作について、福島宣三(参院議員)に見解を問われた末松謙澄は、『初期油彩画では無いか』との回答を寄せた一方、後藤貞行(彫刻家・洋画家)は蘭画の様式に触れたうえで、『ヨーロッパの油彩では無いのではないか』、『古代の画』といった漠然とした見解を遺している。
来歴や絵筋、画題、上部に描かれた数字やアルファベットの様な物の意味など、詳らかでない部分の多い作品である。数字やアルファベット表記は、阿蘭陀由来の絵画にもしばしば存在するが、満洲系の文字に酷似する箇所もあり、こちらも詳細は不明である。
三幅にはそれぞれ、中央に背を向けた人物、向かって右には弓を持ち衣を纏った人物、左には素足のまま袋のような物を提げる人物が描かれている。
右と中央の2名には服飾が描かれているのに対し、左の1名だけは羽織のみを纏った使用人のような出立で、他の2名とは明らかに異なる表現されている。様々資料をあたったが、浅学のため、このような浅黒い肌の描写に類例を見いだせないので、詳しい方よりご教授いただきたい。

茶湯町絵図
作者不詳
江戸時代初期
紙本箔押
個人蔵
30.5 x 56.5 cm
江戸時代初期の風俗画、茶屋風景図。
元は断簡の大きさ、そして画面構成的に推測すると、小屏風また中屏風と言われ比較的小降りな屏風であった事が推測される。
中世より千利休により深まった茶の湯の文化は、戦国の大名などを中心とし、茶の湯を通して一つの社交の場と云うより一国を動かす程の大切なものとなった。
茶の席にて世の中の様々な事柄が大きく揺れ動いた。世の統治は愚か、茶湯に用いる茶道具一つが争いの発端ともなったと云われている。
本図には、各所に江戸初期の作であることをうかがわせる特徴がある。この時期もまだ、戦国時代に引き続き、茶の湯が世を左右するほどの影響力を持っていたが、本図には、日常の中で春に咲く桜を眺め、簡素な茶屋で、茶屋の女性が風炉釜から茶を一服点て、武士とおぼしき男性に茶を振舞っている風景がうかがえる。女性の傍には、風炉、釜、柄杓、茶巾の様な物や、茶筅のと思わしき道具、茶碗、建水などが描かれ、必要最低限の道具にて一服の茶を供する姿が表されている。江戸初期の日常に於いて、どの様に茶の湯が庶民の間で親しまれて居たかを表す数少ない貴重な資料である。
作者不詳
江戸時代初期
紙本箔押
個人蔵
30.5 x 56.5 cm
江戸時代初期の風俗画、茶屋風景図。
元は断簡の大きさ、そして画面構成的に推測すると、小屏風また中屏風と言われ比較的小降りな屏風であった事が推測される。
中世より千利休により深まった茶の湯の文化は、戦国の大名などを中心とし、茶の湯を通して一つの社交の場と云うより一国を動かす程の大切なものとなった。
茶の席にて世の中の様々な事柄が大きく揺れ動いた。世の統治は愚か、茶湯に用いる茶道具一つが争いの発端ともなったと云われている。
本図には、各所に江戸初期の作であることをうかがわせる特徴がある。この時期もまだ、戦国時代に引き続き、茶の湯が世を左右するほどの影響力を持っていたが、本図には、日常の中で春に咲く桜を眺め、簡素な茶屋で、茶屋の女性が風炉釜から茶を一服点て、武士とおぼしき男性に茶を振舞っている風景がうかがえる。女性の傍には、風炉、釜、柄杓、茶巾の様な物や、茶筅のと思わしき道具、茶碗、建水などが描かれ、必要最低限の道具にて一服の茶を供する姿が表されている。江戸初期の日常に於いて、どの様に茶の湯が庶民の間で親しまれて居たかを表す数少ない貴重な資料である。

餅つき図
作者不詳
江戸前期-中期
紙本着色
個人蔵
75.5 x 105.5 cm
江戸時代前期-中期にかけての日常生活の一コマを表した中屏風である。
男たちは上半身裸になり餅をつき、女性はつきたての餅をこわけする図。
臼の横には熱い蒸気が噴き出し餅米を蒸しているシーンが描かれており、祝儀、もしくは年の瀬に賑やかに餅を搗く姿が絵筋良く描かれている。 元は一双の屏風であったであろう。
今では一コマのみになっているが元の姿ではどのようなストーリーが描かれていたのか気になって仕方ない。
作者不詳
江戸前期-中期
紙本着色
個人蔵
75.5 x 105.5 cm
江戸時代前期-中期にかけての日常生活の一コマを表した中屏風である。
男たちは上半身裸になり餅をつき、女性はつきたての餅をこわけする図。
臼の横には熱い蒸気が噴き出し餅米を蒸しているシーンが描かれており、祝儀、もしくは年の瀬に賑やかに餅を搗く姿が絵筋良く描かれている。 元は一双の屏風であったであろう。
今では一コマのみになっているが元の姿ではどのようなストーリーが描かれていたのか気になって仕方ない。


蝦夷アイヌ風俗図 画帳
木戸竹石
生没年不詳
絹本着色
個人蔵
140.0 x 30.0 cm
木戸竹石という人物については函館の絵師とされる文献もある一方で、幕末の津軽藩漢画絵師・平尾魯仙や三上仙年に学ぶという記述もある、漢画技法を用いたアイヌ絵師という以外は詳しい詳しい経歴は不詳とされている。
数少ないアイヌの資料を描く絵師としては中心的人物であり、その上極めて貴重な資料のアイヌ絵師である。
木戸竹石
生没年不詳
絹本着色
個人蔵
140.0 x 30.0 cm
木戸竹石という人物については函館の絵師とされる文献もある一方で、幕末の津軽藩漢画絵師・平尾魯仙や三上仙年に学ぶという記述もある、漢画技法を用いたアイヌ絵師という以外は詳しい詳しい経歴は不詳とされている。
数少ないアイヌの資料を描く絵師としては中心的人物であり、その上極めて貴重な資料のアイヌ絵師である。

クルス紋原案図挟洋紙皮マリア版画
作者不詳
17世紀-18世紀頃
羊皮紙
個人蔵
48.0 x 63.3 cm
先に紹介させて頂いた『隠れ切支丹クルス紋染色図』下より発見された、羊皮紙に銅板にて摺られた作品である。
17世紀-18世紀頃に日本へ舶来した羊皮紙銅板画と思われる、美しい天使たちと聖母マリアの図。
本図に祈りを捧げ、人目を隠すように生きたであろう隠れキリシタンの思いを感じることができる貴重な切支丹遺品である。
作者不詳
17世紀-18世紀頃
羊皮紙
個人蔵
48.0 x 63.3 cm
先に紹介させて頂いた『隠れ切支丹クルス紋染色図』下より発見された、羊皮紙に銅板にて摺られた作品である。
17世紀-18世紀頃に日本へ舶来した羊皮紙銅板画と思われる、美しい天使たちと聖母マリアの図。
本図に祈りを捧げ、人目を隠すように生きたであろう隠れキリシタンの思いを感じることができる貴重な切支丹遺品である。

【勝虫】馬験 旗指物
作者不詳
江戸後期
絹
個人蔵
90.0 x 168.5 cm
江戸後期、松江藩家老家に伝わった馬験である。
馬験とは、武将が馬上や本陣に於いて、長柄に掲げ、所在を明示する旗指物の一つである。
本作は、良質な絹を織り上げた光沢のある仕上がりで、型染めに加え、輪郭の一部には金の箔押し、さらに手彩色を施した上手の馬験である。
武家社会においては、武士や武将が、敵を前に退く、背を見せるのは恥とされていたが、戦場に伴う旗指物のモチーフとして、中世戦国期より縁起物として好まれたもののひとつに、本作に描かれた『蜻蛉』がある。『蜻蛉』は性質上、後ろに退く事が出来ないため、不退転の決意をもって戦に臨むことを表すのに相応しい絵柄とされる。さらに、本作の上部には『叶』の一字があるが、『蜻蛉』(勝ち虫とも称される)のごとく、雄々しく前進し戦に勝つことという、武士の願いが実に明解に表されている。本作に添えられた袋には、江戸時代後期に新調したと記されており、すでに武勲は偲ぶものでもあった時代に、あえて誂えられた軍装品であることがわかる。そこには、武士の誉れに対する憧れと、人生のおける勝利への願いが感じとれるのではないだろうか。
作者不詳
江戸後期
絹
個人蔵
90.0 x 168.5 cm
江戸後期、松江藩家老家に伝わった馬験である。
馬験とは、武将が馬上や本陣に於いて、長柄に掲げ、所在を明示する旗指物の一つである。
本作は、良質な絹を織り上げた光沢のある仕上がりで、型染めに加え、輪郭の一部には金の箔押し、さらに手彩色を施した上手の馬験である。
武家社会においては、武士や武将が、敵を前に退く、背を見せるのは恥とされていたが、戦場に伴う旗指物のモチーフとして、中世戦国期より縁起物として好まれたもののひとつに、本作に描かれた『蜻蛉』がある。『蜻蛉』は性質上、後ろに退く事が出来ないため、不退転の決意をもって戦に臨むことを表すのに相応しい絵柄とされる。さらに、本作の上部には『叶』の一字があるが、『蜻蛉』(勝ち虫とも称される)のごとく、雄々しく前進し戦に勝つことという、武士の願いが実に明解に表されている。本作に添えられた袋には、江戸時代後期に新調したと記されており、すでに武勲は偲ぶものでもあった時代に、あえて誂えられた軍装品であることがわかる。そこには、武士の誉れに対する憧れと、人生のおける勝利への願いが感じとれるのではないだろうか。

IHS綸子地著色聖体秘蹟図指物
作者不詳
16世紀-17世紀初頭
絹綸子
個人蔵
63.6 x 72.7 cm
世界三大聖旗の一つと数えられる天草四郎陣中旗。
1637年の天草島原の乱にて使用された事でも有名な指物である。
艶やかで繊細な綸子に油絵具を用いて描く様式は、天草四郎の陣中旗と同様であるが、本図と天草四郎所縁の旗とは次のように異なる。
天草四郎旗には合唱礼拝する天使が描かれ、本図には、日本で最初に布教した聖フランシスコ・ザビエルの傍らに舞う天使が描かれている。さらに本図の上部には旧ポルトガル語にて、「LOVVAD ○ SEIAOSACTISSIM ○ SACRAMENTO」(いとも尊き聖体の秘跡ほめ尊まえ給れ)と記され、中央にはカリス(聖杯)、その上に十字架をつけたホスチア(聖体)、「ユダヤ人の王ナザレのイエス」という意味の頭文字「INRI」が記される。このように、描かれた内容の差異がある一方で、作品の素材としては、艶やかな生地の綸子が用いられていること、油絵具の質など、いくつか共通する点もみられる。
一説には、本図は、天草四郎陣中旗のプロトタイプにあたるか、もしくは同時期に、天草・島原の乱にて用いられた一揆軍の旗の一部ではともいわれている。天草四郎旗とほぼ同時期、もしくはそれ以前に制作された作品である可能性が極めて高く、詳しい来歴の解明が待たれる。
作者不詳
16世紀-17世紀初頭
絹綸子
個人蔵
63.6 x 72.7 cm
世界三大聖旗の一つと数えられる天草四郎陣中旗。
1637年の天草島原の乱にて使用された事でも有名な指物である。
艶やかで繊細な綸子に油絵具を用いて描く様式は、天草四郎の陣中旗と同様であるが、本図と天草四郎所縁の旗とは次のように異なる。
天草四郎旗には合唱礼拝する天使が描かれ、本図には、日本で最初に布教した聖フランシスコ・ザビエルの傍らに舞う天使が描かれている。さらに本図の上部には旧ポルトガル語にて、「LOVVAD ○ SEIAOSACTISSIM ○ SACRAMENTO」(いとも尊き聖体の秘跡ほめ尊まえ給れ)と記され、中央にはカリス(聖杯)、その上に十字架をつけたホスチア(聖体)、「ユダヤ人の王ナザレのイエス」という意味の頭文字「INRI」が記される。このように、描かれた内容の差異がある一方で、作品の素材としては、艶やかな生地の綸子が用いられていること、油絵具の質など、いくつか共通する点もみられる。
一説には、本図は、天草四郎陣中旗のプロトタイプにあたるか、もしくは同時期に、天草・島原の乱にて用いられた一揆軍の旗の一部ではともいわれている。天草四郎旗とほぼ同時期、もしくはそれ以前に制作された作品である可能性が極めて高く、詳しい来歴の解明が待たれる。
おすすめ
"核"と"根幹"展
第2期 近世絵画の発展
第2期 近世絵画の発展
"核"と"根幹"展
第3期 琳派の流れ
第3期 琳派の流れ
"核"と"根幹"展
第4期 禅僧の画と書
第4期 禅僧の画と書
"核"と"根幹"展
第5期 洒脱
第5期 洒脱
ART SHODO TOKYO作品
橘天敬の絵画1
浮世絵(MET)
印象派絵画(MET)
クリックするとブラウザ上で3DのCGで展示が見られます*
* ローディングに1分以上かかることがあります